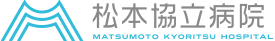総合診療科COMPREHENSIVE
Ⅰ.松本協立病院における総合診療の概要
松本協立病院の内科は、これまで一般内科として開始され、徐々に専門に分化し発展してきました。しかし、その病院の規模と、県内に多数の小病院・診療所をかかえることから、完全に専門に特化することなく、一般内科をしつつ、専門もするというスタイルが定着しました。これはある意味、日本の医療の特徴で、開業医であっても、一般内科以外に自分が得意とする専門分野があるのが普通です。最近の流れの真の意味での家庭医/総合診療科医は、まだほとんど育っていないのが現状だと思います。
では、私たちが求める総合診療科医とはどんなものでしょうか。まず重視すべきは、どこで誰のために医療をするかという視点です。地域によって抗生剤の感受性が違うように、そこの地域の特性を無視して、総合診療は成り立ちません。長野県は、全国の中で高齢化が非常にすすんでおり、入院病床数は少なく平均在院日数は全国で最も短いという特徴があります。高齢者に対する医療知識は幅広く要求されますし、小児科医が少ないため、プライマリーな小児医療も必要です。また、これに加えて、種々の福祉制度の理解、介護保険制度の利用、家族への支援などが要求されます。専門領域の医師が少ないために、総合診療医がある程度の専門医療まで踏み込まざるを得ない状況もあります。
松本協立病院の総合診療は、将来の日本の縮図になるのではないかとも思っています。
Ⅱ.GIO
総合診療科として幅広い疾患を経験し、適切に専門科に紹介できる能力を身に付ける。3年間を通じて専門研修にでる基礎的能力を培う。
Ⅲ.SBO
- 外来で、新患、一般外来を担当し、鑑別診断と適切な検査治療計画が立てられる。
- 外来で、主訴に対する鑑別診断と緊急性の有無の判断ができる。
- 外来で、慢性疾患管理の基本を身に付け、定期的検査計画と患者教育ができる。
- 患者教育ツールの開発ができる。
- 病棟では、内科全般にわたる疾患の、診断と治療について経験する。
- 中等症から重症の内科疾患の管理を経験する。
Ⅳ.カリキュラム
- 1年間は総合診療科を、中小病院で経験する。
- 3年間のうち1年間は、診療所で外来を中心に総合診療を経験する。
- 3年間のうち希望により、マイナー科の研修を経験する。
Ⅴ.週間スケジュール例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | 症例 カンファレンス |
総回診 | 心電図学習会 | 症例 カンファレンス |
輪読会 | |
| 午前 | 外来 | 病棟 | 病棟 | FGS | 病棟 | 外来 |
| 午後 | 病棟 | 外来 | 総合診療科 カンファレンス |
病棟 | 外来 | |
| 夕方 | 総回診 |
Ⅵ.専門研修
- 3年間終了後に、具体的獲得目標を設定して、専門研修施設を選択する。
- 期間は1年間で帰院後の、担う役割を明確にしておく。
Ⅶ.専門医資格
総合診療専門医資格を取得可能です。